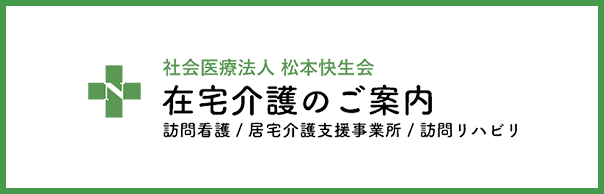病院に通うことが難しくなった患者さんに医療を届けるため、西奈良中央病院では他院に先駆けて訪問診療の取り組みを進めてきました。介護が必要になり外来通院が難しくなった方や、がんの末期で外出がつらくなった方などに対して、ご自宅での診療を通じて「その人らしい生活」を支える体制が整っています。訪問診療のニーズが全国的に急増する中、西奈良中央病院が担う役割はますます重要になっています。診療科をまたぐ医師間の連携、多職種による連携、法人内事業所との連携など、患者さんとご家族が安心して「家で過ごす」という選択ができるよう支えています。
訪問診療の現場
― 訪問診療のニーズは年々増えているのでしょうか。
そうですね。日本が超高齢社会を迎え、訪問診療のニーズが非常に増えてきています。地域を見渡しても、ここ数年で在宅医療専門のクリニックが増えているだけでなく、私たちのような規模の病院でも訪問診療を開始する病院が増えてきています。
― 在宅医療専門のクリニックと、西奈良中央病院との違いを教えてください。

病院であることが大きな強みです。患者さんの多くは西奈良中央病院に入院されたことのある方や、外来に通院されていた方で、「いざという時にはまた病院で診てもらえる」という安心感を持っておられます。そのため、在宅医療専門のクリニックとは異なり、「どんなことがあっても必ず自宅で」というケースはそれほど多くはなく、「調子が悪くなったら病院で診てもらう」という選択肢を持ちながら訪問診療を受けている方が多いのが特徴です。
緩和ケアと訪問診療
― 緩和ケア病棟と連携されていると伺いました。
緩和ケア病棟との連携は重視しています。
緩和ケア外来に面談に来られる方の多くは、「できるだけ家で過ごしたいけれど、いざというときは緩和ケア病棟に入院したい」という気持ちを持っておられます。
訪問診療を受けながら自宅でできる限り過ごしていただき、状態が悪くなり自宅で過ごすことが難しくなった際にはスムーズに連携して入院までつなぐことができるのが、私たちのような病院を母体とした訪問診療の利点です。
また、一旦入院したとしても再び自宅に帰ることも可能です。その際もスムーズに連携して退院につなげることができます。
多職種間だけではない、法人での連携体制
― 専門職連携に力を入れていると伺いました。
院内には各科の医師だけでなく、緩和ケアチーム、リハビリスタッフ、心理士、栄養士といった専門職も在籍しており、必要なときにはすぐに連携できる環境が整っています。こうした体制は、病院を母体とした訪問診療だからこそ可能な連携だと感じています。
また、当院で複数の診療科にまたがる治療を受けておられた患者さんが、外来通院が難しくなり、訪問診療に移行するケースがあります。その場合、これまでのように毎月各科の医師に診察してもらえないことは患者さんのデメリットになりえますが、必要に応じて各科の医師にすぐに相談することはできますので、患者さんのデメリットを極力減らしながら通院の負担を減らすことができることも病院からの訪問診療ならではと考えます。
― 法人内での連携について教えてください。
西奈良中央病院は、同一法人内に訪問看護ステーションやケアプランセンターや介護老人保健施設(老健)を持っており、医療と介護両面において連携が可能です。
訪問看護師やケアマネージャーとともに在宅での生活を支えつつ、患者さんやご家族の希望に応じて老健のショートステイや通所サービスを利用していただく、というように、法人内の資源を活かしながら柔軟に介護サービスを提案することができます。
「その人らしい最期」を叶えることの難しさ
― ACP(アドバンス・ケア・プランニング)を行う上で、どのようなことを大切にしていますか。
ACPにおいては、大前提として患者さん本人の希望を尊重することが何より大切です。しかし、それはご家族との関係性や、これまでの暮らしの中で積み上げられてきた背景が影響することを理解しておかないとうまくいかないことが多いと感じています。特に在宅医療においては「最期をどこで迎えるか」ということが非常に大切な選択であるとともに難しい選択になることがあり、もし患者さんが「最期まで家で過ごしたい」と希望しても、ご家族がそれをどう受け止めるか、ということが非常に重要になると感じています。
ご家族に負担をまったくかけることなく、医療や介護サービスだけを利用して自宅で最期を迎えることが理想ですが、現実的にはご家族にそばにいていただくことが必要になるケースが多いためです。
超高齢社会においては、患者さんだけでなくご家族も高齢であることが普通であり「自分のことで精一杯」とおっしゃるご家族もたくさんいます。若いご家族であれば、仕事や子育てをされている方もいます。そのうえでの介護となると、夜間のケアや急変時の対応など、多くの不安をお持ちになるでしょう。
「自宅で最期まで過ごしたい」という願いは自然な願いです。
しかし在宅医療に関わる人たちの中には、「自宅で最期まで過ごさせてあげないのは悪」という風潮も一部にあり、それがご家族を苦しめるケースもあると感じています。
患者さん本人の意思を尊重することが大切なのですが、ご家族の身体的な負担や精神的な負担も考慮に入れる必要があるわけです。それを無視して「本人の希望を叶えるべきだ」と言い切ってしまうと、かえって誰も救えないケースも出てきてしまうかもしれません。
「納得」を支える医療
― ACPのゴールって何だと思いますか。

最期に患者さんやご家族に「これでよかった」と思っていただけるかどうかだと思います。
患者さんとご家族で話し合った結果、最期まで自宅で過ごした方も、入院して最期を迎えた方も、一旦入院したものの退院して最期は自宅で迎えた方もみてきました。
「最期まで自宅で一緒に過ごせてよかった」「最期は病院でみていただけたので安心できた」とご家族に声をかけていただいてきました。
このように、最期をどこで迎えたとしても患者さんとご家族が「よかった」と思えるよう、医療従事者はそっと支えることが大切だと思います。患者さん本人に寄り添いすぎて家族の生活を無視するわけにもいかず、ご家族に寄り添いすぎて本人の希望を無視するわけにもいかないわけですから、私たちが結論を出すわけにはいきません。しかし、最後まで支えてくれる人がいる、選択を一緒に考えてくれる人がいる、それだけで少し救われる気がする、そんな存在でありたいと思っています。
ACPとは、最期の意思を記すことだけではなく、患者さん本人とご家族が「自分たちの選択だった」と思えるように、そっと背中を支える行為なのかもしれません。