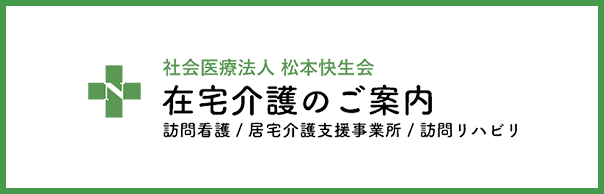介護老人保健施設「大和田の里」では、訪問歯科との連携による専門的な口腔衛生管理の取り組みを進めています。口腔内の健康を保つことが、利用者の身体機能や意欲、QOL(生活の質)にどのように関わっていくのか、また訪問歯科との連携によってどのような変化があったのかを、多職種の視点でお伺いしました。
口腔の健康と心身の健康
― 口腔衛生と利用者との健康にはどのような関係があるのでしょうか。

歯科医師
口腔内が不衛生であれば、歯周病菌が全身にまわり、脳卒中や糖尿病、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。食欲も低下し、身体面・精神面ともに悪影響を及ぼすこともあります。そのため、日常的な口腔状態の把握は必要であり、口腔内の課題に対してケアをしていくことが必要です。
歯科衛生士
お口は健康の入り口です。口腔内が汚れていると、誤嚥性肺炎や十分な栄養を取り入れることが難しい状態になります。日常的な口腔ケアの積み重ね、口腔内を清潔に保つことや、口腔機能を改善することが、高齢者にとって極めて大切なのです。
管理栄養士
口腔衛生を管理することは、栄養改善に向けてとても重要です。歯の状態が良くなることで食事の咀嚼・嚥下機能も改善され、栄養をしっかり摂取することができ、リハビリによる筋力回復の効果が出ます。その他にも、意欲の向上や、認知機能が安定したりしたご利用者様もいます。
介護支援課課長 (主任ケアマネ―シャー・支援相談員)
大和田の里にご入所いただく際、入所前にご利用者様のご状態の確認をしたときに、栄養状態や口腔状態が不十分な方が多くみられます。口腔状態が悪いと食べる意欲も低下することもあり、その結果低栄養状態で運動をしても筋力がつかなかったり、誤嚥性肺炎のリスクも高まります。そこで、口腔衛生管理、栄養マネジメント、機能訓練が一体となり、連携してご利用者に関わることで、利用者様の健康を保ち、心身機能の維持向上を図り、生活の質を向上させることが、老健の役割と考えています。
「食べること」が表情を変える
― やはり「食べる」ということは大切なのでしょうか。

療養課課長(看護師)
利用者の「食べたい」という気持ちを尊重することが大切です。実際、口から食べ物の摂取ができない胃ろうの方でも、食べ物の匂いを感じると「食べたい」という気持ちが起こります。そうした方々にも、煮魚やスープの匂いを嗅いでもらったり、煮汁をスポンジに浸して舌に載せたり、少しだけでも「食事」を体験していただいています。すると、自分の意思を取り戻すかのように表情が変わるようになりました。そこから、「何を食べたいか」とリクエストをしたり、自ら要望を仰ったりするようになりました。
言語聴覚士
「危ないから食べさせない」ではなく、「少しでも口から味わってもらう」工夫が重要だと感じています。 栄養摂取という面では大きな違いはありませんが、食べる意欲そのものが、その人の生きる力を引き出します。
口腔ケアからのアプローチ
― 「大和田の里」ではなぜ口腔ケアを重視するようになったのでしょうか?

言語聴覚士
介護の中で口腔ケアは当たり前に行うべきものだと考えています。高齢者の口腔機能の衰え、いわゆる「オーラルフレイル」は社会的孤立にもつながります。口臭が出たり、ろれつが回りにくくなったりすると、人と話すことに対して消極的になる方もおられます。そこから社会性が減少し、外に出ることが少なくなり、身体機能も悪化の恐れもあります。その連鎖を食い止めるのにも、日常的な口腔ケアは重要です。「大和田の里」では早くから「口腔ケア委員会」を設置し、以前から全職員で口腔ケアに取り組んできました。今では歯科医師や歯科衛生士とともに、勉強会を重ね、施設全体の意識向上、チーム間の連携力向上に取り組んでいます。
― 訪問歯科が来られるようになって、何が変わりましたか。
療養課長(看護師)
利用者自身の意識が変わりました。ある方は、口腔状態の改善とともに、「私はコーヒーが好きで、どこの豆がいい。」「砂糖を入れないで、ミルクは入れて」といった具体的な要望をおっしゃるようになり、認知機能面で大きな変化がありました。それによって介護職員のやりがいにも繋がり、施設全体の意識向上を感じています。

言語聴覚士
他にも、リハビリに使える時間が増えました。今まではリハビリの時間に口腔ケアも行っていましたが、歯科衛生士さんに来ていただいたことで、嚥下訓練に使える時間が増えました。効率も成果も上がっています。
歯科衛生士
多職種間での口腔ケアへの理解や、利用者さんの意識の変化もあり、この半年で口腔状態が非常に整ってきた方が多くいらっしゃいました。
介護支援課課長 (主任ケアマネ―シャー・支援相談員)
その成果は数値にも表れており、肺炎患者が格段に減りました。昨年、誤嚥性肺炎を発症した方は1年間で6人いましたが、歯科衛生士さんが来られてからは、半年で1人だけでした。歯がきれいになることで、ミキサー食から刻み食、普通食が食べられるようになり、利用者さんの喜びにもつながっています。
多職種連携での口腔ケア
― 多職種で連携して口腔衛生に取り組んでいると伺いました。

歯科医師
現在口腔内を刺激し、嚥下機能を高める機器も導入しています。今後、今まで以上に、口腔機能が向上し、誤嚥性肺炎を予防しながらおいしく食事をすることが出来ればいいと考えています。
言語聴覚士
歯科医師さんによる口腔内のアセスメントや、義歯の調整をしていただいた際は、管理栄養士と食事の形態の相談について話し合います。また、ご利用者様の意思も尊重し、介護士さんを交えて、口腔のリハビリや食事の内容の変更にリアルタイムで反映しています。

療養課長(看護師)
口腔ケアの施行率や口腔乾燥、出血、舌苔の有無など、口腔ケアに関する情報は事細かくカルテに記録しています。だからこそ、すぐに対応できるようになり、多職種間での連携でより良いケアにつながっています。
介護支援課課長 (主任ケアマネ―シャー・支援相談員)
大和田の里では在宅復帰・在宅支援にも力を入れており、医師、看護師、セラピスト、管理栄養士、介護職、施設ケアマネ―ジャー、それぞれの専門職が、ご利用者やそのご家族様へ、退所後の生活に向けたアドバイスを行っています。在宅復帰された後も、利用者の栄養状態や口腔状態が悪化しないよう、歯科衛生士が定期的にフォローアップ訪問を行い、ご家族への口腔ケア指導も継続しています。
大切な人に「安心」と「笑顔」を

大和田の里では、多職種が連携し、“食べること”の楽しみにも重点を置き、専門性の高い医療・介護サービスを提供することで、ご利用者様が望む生活を送ることが出来るように、心を込めてご支援させていただいています。目の前には丸山古墳があり、自然豊かな地で、誰もが大和田の里でサービスを受けたい、と思っていただけるように、今後も、ご利用者様とそのご家族の立場に立ったケアの提供を、職員一同大切にしていきます。