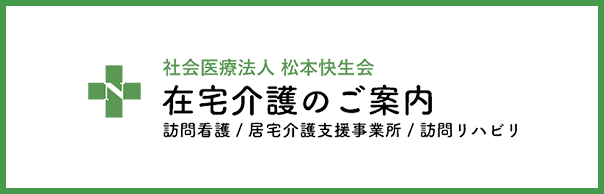在宅から施設までをサポートする訪問リハビリ
― 具体的には、どのようなスタッフが、どこへ訪問するのですか?

当院の訪問リハビリテーションは、理学療法士(PT)、言語聴覚士(ST)で業務にあたっています。その内半数は経験年数10年以上のスタッフで、PTとSTが連携し、院内のスタッフとも相談しながら訪問リハビリを提供できることが当事業所の特色です。訪問リハビリを必要とされる方は、整形外科の病気だけでなく、内科疾患や誤嚥性肺炎、脳梗塞など様々です。言語聴覚士がいることで、話す練習(高次脳機能障害に対する構音訓練)や、摂食嚥下訓練といったリハビリにも対応しています。
利用者ごとのリハビリの内容によって、PTのみ、STのみ、またはPTとSTが交互に伺いどちらのリハビリも合わせて提供するなど、柔軟な対応が可能です。今後は、作業療法士(OT)も訪問リハビリに加わっていく予定となっていますので、一人ひとりのニーズに合わせたセラピストの派遣を通じて、さらに細かなニーズに応えていくことができるようになります。
在宅への訪問はもちろんですが、高齢者施設へ訪問リハビリに伺うこともあります。また、入院を機に自宅から施設に入所されたとしても、継続して訪問するケースも増えてきました。
― 他にはどのような特徴がありますか?
当院の訪問リハビリテーションスタッフは院内で様々な疾患に対する経験を積み、知識やスキルを高め、病気の状態などを十分理解した上で訪問リハビリを提供しているので、退院調整をしているソーシャルワーカーから「こちらの患者さんに退院後の訪問リハビリは対応可能ですか?」という相談が来た際はスムーズな連携が可能となります。
利用者一人ひとりに合わせた訪問リハビリを丁寧かつスムーズに提供できることは、利用者やご家族にとって大きなメリットになると考えています。
在宅に訪問するリハビリセラピスト ~実際に訪問リハビリに携わってみて感じたこと~
― 訪問リハビリに従事するリハビリセラピストのやりがいは?

理学療法士の約8割は、病院等で勤務していると言われています。しかし、それらの医療機関から訪問リハビリに従事しているセラピストはまだまだ少ないのが現状です。私は入職してから約4年間、病院内で業務をしてから訪問リハビリへ配置転換となりました。
最初は利用者宅へ直接訪問することに慣れないことや、訪問時に起きたアクシデント等に対し、自分で責任をもって対応する必要があること、前任者との比較も気になり、精神的にも肉体的にも疲労困憊になることがありました。しかし、「利用者が住み慣れた環境で生活を継続するには、どのようなリハビリがよいのか?」を考え、じっくり向き合っていくうちに、利用者やご家族から「ありがとうね」「また来てね」「来てもらえてよかったわ」等の言葉をかけていただくことが増えました。それらの言葉を励みに今はやりがいを持って業務を行っています。
― 在宅への訪問の際に、気を配っていることは?
高齢で一人暮らしの方への自宅訪問は、定期的な安否確認にもなりますし、体調はどうか、こけたりしていないか、熱中症の心配はないか、お薬をちゃんと飲まれているかなど、そういったことも確認しています。自宅での療養生活がスムーズにおくれるよう、治療+サポートもさせていただくという視点を持って訪問リハビリを行っています。
訪問リハビリで伺った際、顔色が悪く、痰で喉がゴロゴロしている時は、訪問看護に電話をして痰の吸引に来てもらうなど、訪問看護と連携を取りながらサポートをしています。訪問リハビリのセラピストにできることは、ただリハビリを在宅で提供することだけではないということも、やりがいにつながっています。
在宅は、リハビリテーション医療の最前線
― 訪問リハビリに従事していて、リハビリテーションに対する考え方にも変化があったそうですね。
リハビリテーションという言葉の語源には、「再び人間らしく生活できるようになる」という意味があります。
そのため、利用者が実際に生活されている環境で、日常生活動作の改善、生活の質の向上が必要となってきます。病院を出て実際に在宅を訪問することで、「リハビリテーションは生活の中に溶け込むことで本来の価値を見出すことができる」と感じます。そうした経験から、今では在宅こそリハビリテーション医療の最前線なのではないかと考えるようになりました。
― 在宅ならではの特徴はありますか?
入院中の院内リハビリは「家に帰りたい」というのが一番大きな目的ですが、在宅でのリハビリの場合は「家に帰れたから、次は洗濯物が干せるようになりたい」「料理ができるようになりたい」など、生活の中でのより具体的な目標に変わってきます。その目標や環境に合わせてリハビリプランを立てていき、普段生活をされている実際の場所でリハビリをすることに大きな意義を感じています。
当院の訪問リハビリの強み、特徴について
― 病院から訪問リハビリに出る強みはありますか?

病院の訪問リハビリだからこその強みは、2点あります。まず1つめの強みは、リハビリ診察、リハビリ会議を定期的に行い、多職種でマネジメントしている点です。当院から訪問リハビリを提供するにあたり、リハビリテーション医師の協力のもと、リハビリテーション計画(具体的な目標等)を立てて、利用者に訪問リハビリを提供しています。医師と協力し、ケアマネジャー、訪問看護等の多職種と連携をとり、多面的に利用者一人ひとりに合わせた計画を立てて対応するので、安心して訪問リハビリを利用いただくことができます。
3カ月に1回のリハビリ会議で「この3カ月でこんなことができるようになった」「ちょっとこけてしまった」などを共有し、利用者と現状の確認、状態をしっかりと把握します。そして、それらの内容を踏まえて、また次の3カ月後の目標を一緒に立てていきます。訪問リハビリスタッフだけで振り返って目標を決めるのではなく、医師も同席して、利用者とご家族も一緒にみんなで決めていくところが一番大きな特徴だと思います。
― 2つめの強みは何ですか?
2つめの強みは、医療保険を利用した短期間に集中的なリハビリテーションを提供している点です。訪問診療を利用している方で、直近1カ月の間に日常生活動作能力が低下している等の条件はありますが、条件を満たした方を対象に、介護保険ではなく、医療保険を利用して、短期間(14日間)で概ね毎日訪問リハビリを受けていただくことができる体制を整えています。
例えば退院直後、自宅での生活が不安で、慣れるまでの間リハビリをして欲しい方や、自宅内で体調を崩し、動けなくなったからリハビリをして欲しいなどのニーズがあった際、主治医の指示の下、医療保険を利用して頻回のリハビリを受けていただくことが可能なケースがあります。短期間でも集中的にリハビリを実施することで、実際に日常生活動作能力が改善し、外出することができるようになった方、車椅子生活であったが自宅の中を歩いて移動できるようになった方もおられます。
このように住み慣れた環境下で集中的にリハビリを継続することで、退院後も安全に生活を送ることができるようになります。
今後の展望について
― 今後の展望を教えてください。

高齢の方々が住み慣れた地域・環境で生活を継続できるように、これからも貢献していきたいと考えています。今後は訪問リハビリの利用が増えてくると予想されます。その需要に応えるためにも、私が感じたことや、やりがい等を後輩のスタッフやこれからリハビリスタッフを目指す学生にも感じてもらい、訪問リハビリに少しでも興味、関心を持ってもらい、訪問リハビリに従事するセラピストが増えることにも貢献していければと思います。
当院では近く、訪問リハビリのスタッフに作業療法士も加わっていく予定です。訪問リハビリの現場で最近よく感じるのは、転んで手をついた際に手首を骨折してしまったという高齢の方が、退院後に普段の生活に戻って「料理で包丁を使いたい」「縫物がしたい」といった時に、より専門的な手のリハビリを提供することができればもっといいのになということ。怪我はなくても高齢によって手先が使いづらくなるという悩みは多くの方にあるものですので、手外科の医師との連携のほか、手のプロである作業療法士がチームに加わることで、一層生活に根差した訪問リハビリへと充実させていくことができると思っています。
― 地域の中での「切れ目のない医療」についての想いを教えてください。
入院されている方が、退院後も引き続きリハビリを必要とされる際に、住み慣れた地域の中で充実した訪問リハビリを受けられる環境があることはとても重要です。当院の患者だけでなく、他の病院に入院されている方でも、当院の訪問リハビリを希望される場合は、退院支援の段階から訪問リハビリのセラピストがカンファレンスに参加しリハビリプランを立てていくことができる仕組みがありますので、病院の垣根を超えた連携を通じて、地域の中での切れ目のない医療を一緒に支えていけたらと思っています。
「訪問リハビリを利用するのであれば、西奈良中央病院にお願いしたい」と言っていただけるように、日々の研鑽を怠らず、利用者一人ひとりに満足していただけるリハビリテーションを提供していきたいと考えています。